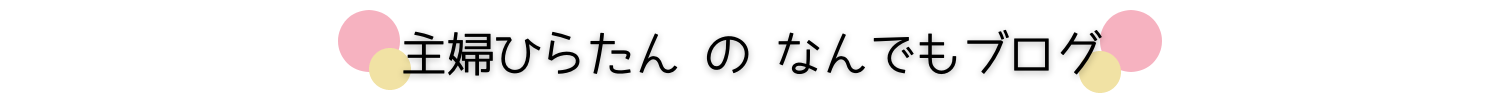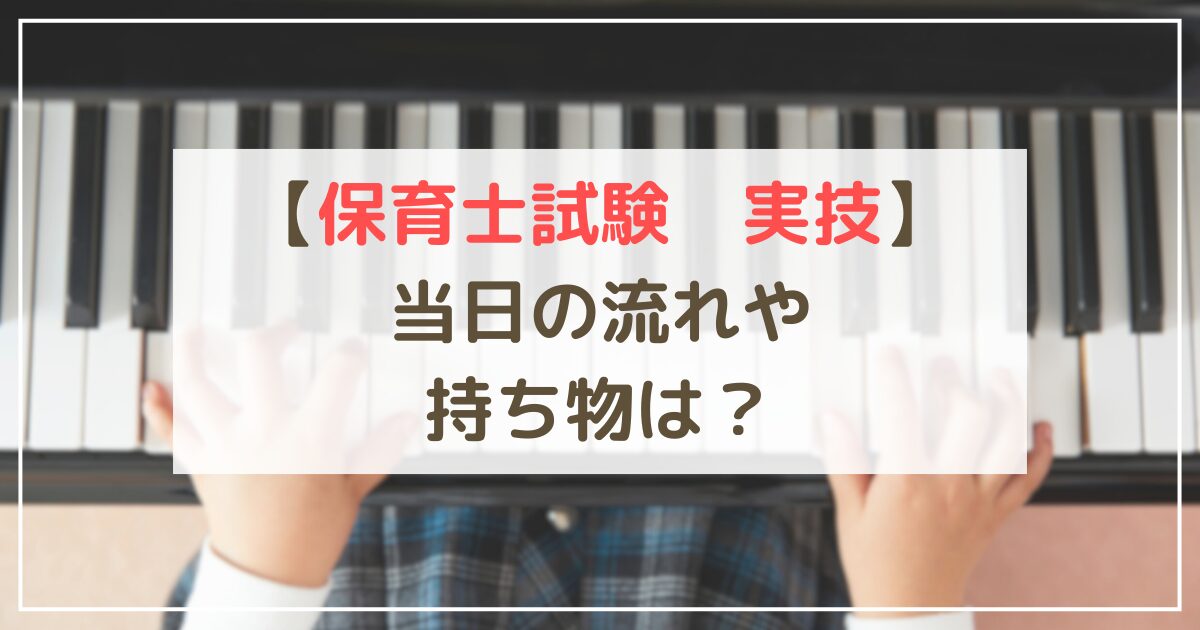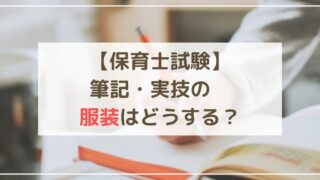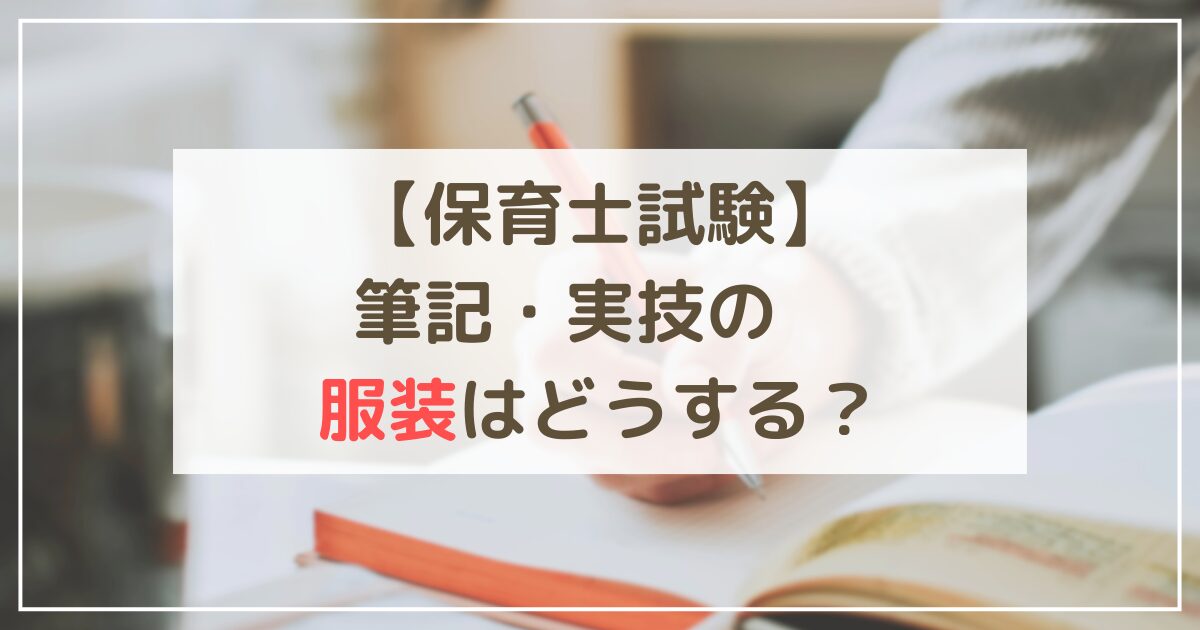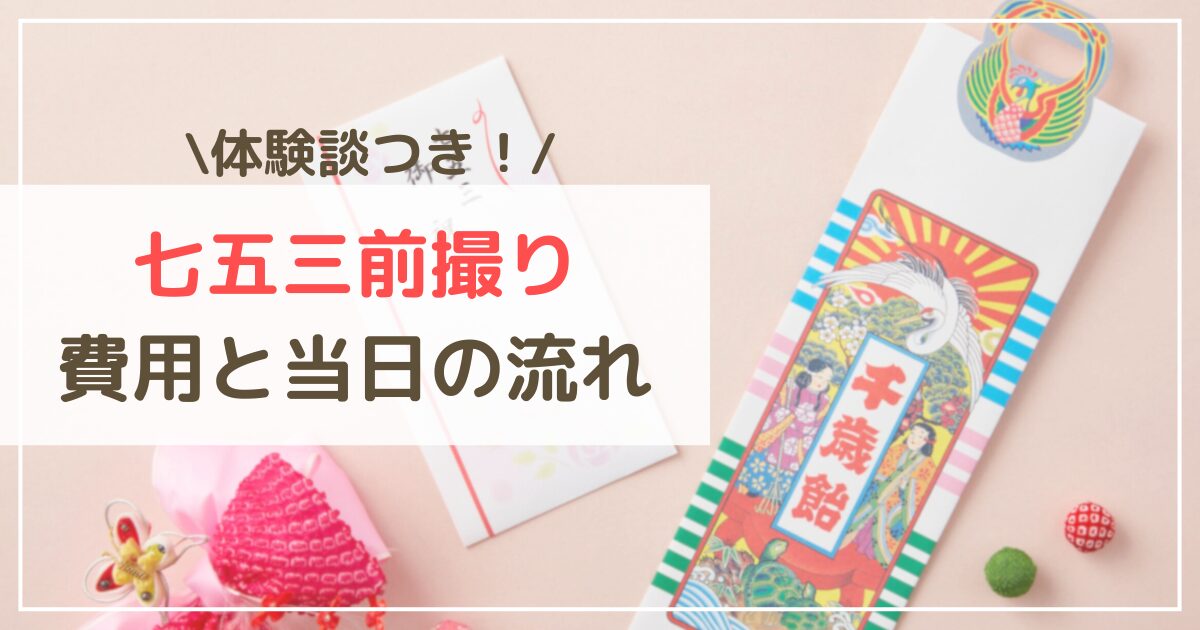こんにちは、主婦ひらたんです。
先日令和7年度の保育士試験を受験し、無事合格しました!
保育士実技試験は、事前に課題の練習をしていても「当日の流れ」がイメージできないと不安になりますよね。
私自身も

- 当日はどんな流れなのかな?
- 試験官はどこに座っているのだろう、、
- 何を持っていけばいい?
などとても悩みました^^;
実際に試験当日はとても緊張しましたが、事前にシミュレーションしていたことで落ち着いて臨むことができました。
この記事では、私が実際に音楽と言語を受験したときの経験をふまえて
- 当日のスケジュール
- 試験の流れ
- 持ち物
についてまとめています。
これから実技試験を受験される方はぜひ参考にしてみてくださいね。
会場到着まで
試験会場にはガイダンス開始の30分前までに到着しておくのがおすすめです。
受験票には「ガイダンス開始時刻の30分前から入場可能」と記載があります。(※会場によって異なる場合あり)
私の場合はこんな感じでした。
- ガイダンス開始時刻:9時00分
- 入場開始時刻:8時30分
- 実際の到着時間:8時30分頃
会場までは電車+バスを利用しましたが、遅延があっても慌てないよう、余裕をもって出発しました。
特にバスは利用者が多く、バス停には行列ができ、車内も満員状態でした^^;
また、私の試験会場は大学で、バス停からガイダンス会場まで少し歩く必要がありました。
そういった点も含めて、移動時間は少し多めに見積もっておくと安心です。
試験の全体的な流れ(音楽・言語)
- ガイダンス会場に到着した順に着席
- ガイダンス開始
- 試験開始20分前までに待機室で待機
- 順番が近づいたら試験室前で待機
- 試験
試験開始の20分前までは休憩室や待機室で過ごし、その後は呼ばれるのを待つ流れになります。
待機室では順番が近づくと試験室前に移動するよう案内されました。
自分の予定していた試験開始時間よりも早まることもあるので、20分前までには必ず待機室にいるのが安心です。
特に試験室前で待っている時間は、正直いちばん緊張しました…。心臓がバクバクして落ち着かず、ソワソワしっぱなし(笑)。
でも、いざ試験が始まってしまうと、気づけば「あれ?もう終わり?」というくらいあっという間でした。
音楽表現の流れ
私が受験したときは、入室 → 荷物を置く → 受験番号シールを試験官に渡す → 弾き歌い開始、という流れでした。
会場によって異なりますが、私のときは試験官に背を向けて弾き歌いするスタイルで、表情がどこまで見えているかは分からず…。
それでも声で気持ちを届けられるように、なるべく笑顔を意識しました。
実際は笑顔はできていなかったですが…^^;笑
演奏後は「ありがとうございました」とお辞儀をして終了。
時間にすると本当に一瞬で、気づけば終わっていた、という感覚でした。

試験室前での待機中って、他の人の演奏が丸聞こえなのかな…?
と不安でしたが、私の会場ではピアノの音が少し聞こえる程度で、思ったより気になりませんでした。
実際に受けてみて思ったのは、試験官と向き合う時間はごくわずかだからこそ、第一印象がとても大切だということです。
服装や姿勢も含めて「子どもと接する保育士らしい雰囲気」を意識して臨むと安心ですよ^^
ちなみに私が受験したときは白ブラウス+黒パンツ+黒ローファーで臨みました。
似たデザインはこちらでチェックできます↓
ミスタッチや音程のズレは大丈夫?
ミスタッチや音程がズレてしまったらどうしよう…と不安になりますよね。
私も弾き歌いのときに一箇所ミスタッチがあり、歌も音程が外れているところがあったかと思います^^;
でも、止まらずに最後までやりきることを意識した結果、合格できました。
採点基準は分からないですが、「子どもに向き合う姿勢」や「最後までやり通す力」を意識するのがポイントかなと思います。
多少のミスは気にせず、自信を持って笑顔で最後まで演奏をやりきることが大切だなと感じました◎
言語表現の流れ
言語も音楽とほとんど同じ流れで、進行はこんな感じでした。
入室 → 荷物を置く → 受験番号シールを試験官に渡す → 課題が指定される → 素話開始

待機場所では「何か話しているな…」と聞こえる程度で、内容までは分かりませんでした。
実際に試験官の前に座ると、その場で課題が告げられるので、一瞬頭が真っ白になりそうに(笑)。
それでも落ち着いて自信を持って話し始めたら、最後まで止まらずに話せました。
話し終えた時点で、体感では2分55秒くらいだったかなと思います。
練習のときからストップウォッチで時間を測っておくと安心ですよ◎
私は「緊張すると早口になるだろうな」と思っていたので、意識的にゆっくりめに、子どもたちを見渡すように話しました。
また、本番では練習通りの台本や言い回しにならないこともあります。
「完璧に台本通り!」よりも「ストーリーの流れを頭に入れておく」ことが大切。
セリフが少し違っても、慌てず立て直すことができますよ。
持ち物リスト
私の当日の持ち物はこちら↓
- 受験票
- 台本(音楽・言語)
- 筆記用具
- 腕時計(スマートウォッチ不可)
- 財布・スマホ
- ハンカチ・ティッシュ
- 日傘(折りたたみ傘)
- カーディガン
- 飲み物
- 昼食や軽食
受験票は絶対に忘れないようにしましょう。試験番号シールを使うので、とても大切です。
また、当日のガイダンスで自分の試験開始時間が分かります。
朝から夕方までかかる人もいるので、昼食を用意しておくか、近くにコンビニなどがあるかを確認しておくと安心です。
さらに、のど飴などちょっとしたケア用品もあると心強いですよ^^
まとめ
保育士実技試験は、実際に受けてみると驚くほどあっという間に終わります。
だからこそ、服装や持ち物を整えるだけでなく、事前にしっかり練習して自信をつけておくことが大切です。
仕事や家事、育児などとの両立をしながらの練習は大変ですが、繰り返し取り組むことで、当日は少しの緊張でも落ち着いて力を出せます。
試験では多少のミスがあっても笑顔で最後までやりきりましょう!
▼当日の服装について詳しく知りたい方はこちら
この記事がこれから保育士実技試験を受験される方の参考になれば幸いです◎
最後までお読みいただきありがとうございました。